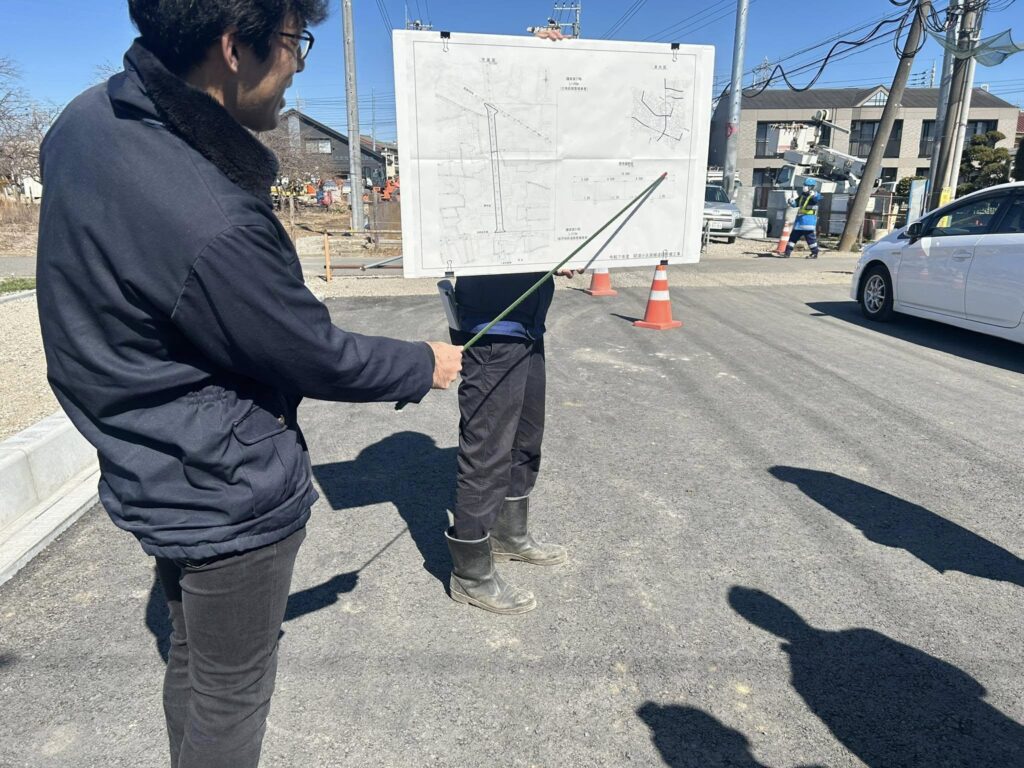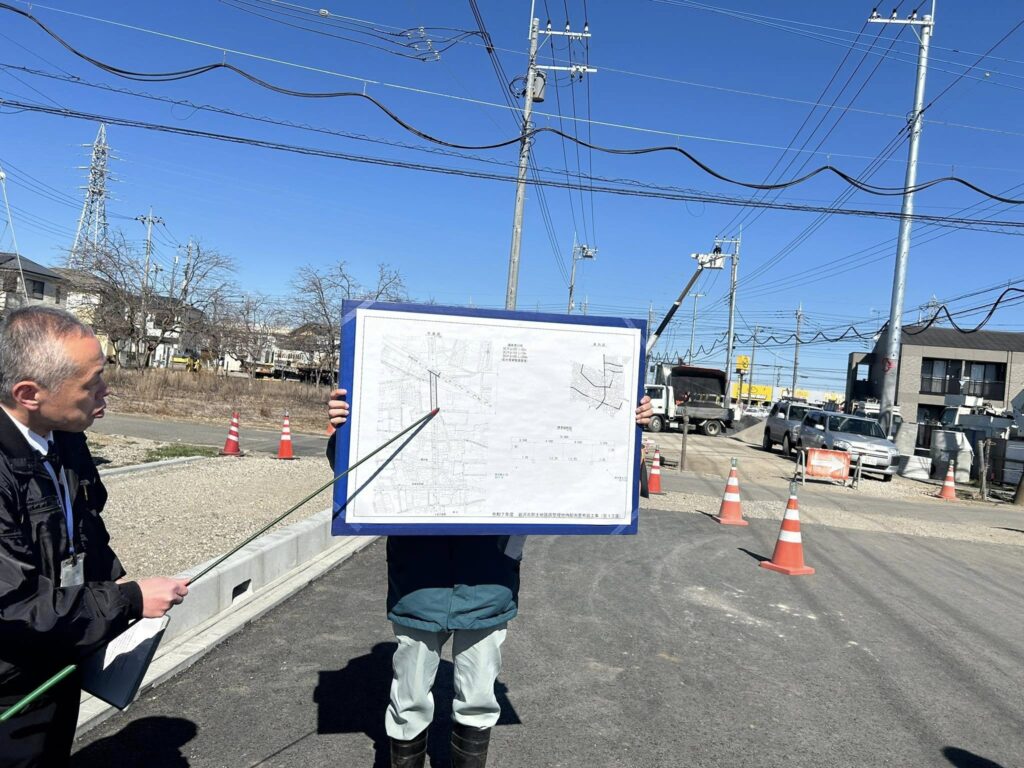経済建設委員会。
令和7年2月25日午前10時より全委員、執行部出席の下開会、直ちに休憩し、審査に必要な現地視察を行い、午後1時に再開、付託された議案の審査を行いました。
以下、質疑等で明らかとなりました主なものについてご報告いたします。
議案第10号
質疑では、法律施行令を引用する条ずれを整理するための改正であり、規制や内容についての改正はないこと等が明らかとなりました。
以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、議案第10号は全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第13号中 本委員会付託分
質疑では、
6款農林水産業費、1項農業費、3目農業振興費について、支援対象者をサポートチームで定期的に巡回・指導してきたが、作付を行ったものの収穫ができず、認定を見送る判断となったことから、対象者1名の減額となったこと、
7款商工費、1項商工費、1目商工総務費について、今年度のふるさと納税は令和6年12月末までに寄附総額約1億1000万円、前年度比約42%の減少であること、要因は指定制度改正により主要返礼品のムーミングッズが対象外となったことと考えていること、返礼品の充実はすぐに結果が出ないので広告効果が測られるよう試みていること、
8款土木費2項道路橋りょう費、2目道路維持費について、舗装打ち換え工事は、社会資本整備総合交付金を財源としており、国の補正予算の配分があったため、市でも補正予算を組んで事業の前倒しを行うとしたこと等が明らかとなりました。
以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、議案第13号中、本委員会付託分は全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第15号
質疑では、事業費の工事請負費は、国の補正予算の配分があり、6メートル幅員の道路3本の追加工事であること、未整備箇所において、六道交差点付近は下水道原町幹線の処理が懸念材料、佐瀬病院交差点から佐瀬踏切までは、上水道幹線の整備と地権者の合意が得られていないこと、複数路線を一体的に整備することは予算の関係で難しいこと、等が明らかとなりました。
以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、議案第15号は全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第16号
質疑では、事業費の工事請負費と補償金の減額は、双柳南部は国庫補助金の内示が見込みより低かったことや保留地の公売に希望者がなく、歳入確保が難しくなったためであること等が明らかとなりました。
以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、議案第16号は全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第17号
質疑では、事業費の工事請負費と補償金の減額は、双柳南部と同様で歳入確保が難しかったためで、年度当初の国庫補助金内示率は、都市再生区画整理事業では7割を下回り、道路整備に関するものは5割を下回ったが、年度途中の過不足調査等には積極的に手上げをし、財源確保を行ったこと、等が明らかとなりました。
以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、議案第17号は全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第18号
質疑では、岩沢南部でも同様の理由で歳入確保が難しかったが、地権者と補償交渉が進んだ個所もあり、財源確保に苦慮しながらも当初予定を変更して事業停滞がないよう取り組んでいること等が明らかとなりました。
以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、議案第18号は全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第19号と20号は関連があるため一括して議題とし、質疑では
市道の廃止については、申請書に図面や隣接地所有者の承諾書の添付が必要であり、近隣への説明や自治会の同意と合わせて確認を行っていること等が明らかとなりました。
以上で質疑を終結し、両案とも討論はなく、採決の結果、議案第19号は全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に採決の結果、議案第20号は全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第22号
質疑では、無償譲渡となったきっかけは、建物を自己所有にすることでグレードアップしたいとして相手方から譲渡を希望する申請があったこと、本施設は飯能市公共施設等総合管理計画により、財産処分を前提とした協議を進めていたため、修繕等でブラッシュアップして民間企業に賃貸借するなどの考えはなかったこと等が明らかとなりました。
以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、議案第22号は全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第23号中 本委員会付託分
質疑では、
4款衛生費、2項環境費、
1目環境総務費について、市民清掃デーは市民憲章に基づいて実施しており、自治会未加入世帯も無理なく実施できる意義があること、犬の登録事業は、市で行き場を失った飼い犬に関する相談は受付けておらず、保健所の管轄であり、引き取り等は難しいと思われ実態把握はできていないが、県と情報交換や意見交換をしていきたいと考えていること、
2目環境対策費について、住宅用省エネ設備推進補助金は、過年度の実績を踏まえ今年度予算より減額して対応すること、
騒音振動調査は5年ごとに調査地点を変更しており、新たな3地点が調査予定であること、国道299号沿いの地点も含まれること、不正改造車両等の突発的な音は除き通常の自動車が通常の走行時の音を調べるものであること、不正改造車両等は調査以前に違法であり、警察に取り締まり強化の要望を出していること、
3項清掃費、1目清掃総務費について、本市クリーンセンターでもリチウムイオン電池による発火事故は発生しており、安全対策のセンサー等により初期段階で発見され大事には至っていないが、今後も周知啓発を続けていくこと
2目塵芥処理費について、最終処分場施設管理運営事業では、旧処分場とその管理地の利活用は現時点では考えておらず、最終処分場廃止までは適切な管理をしていくこと、廃止には多くの基準があり廃止の見通しは立っていないこと、
3目し尿処理費について、汲み取り世帯数は推計918世帯、減少傾向であること、
6款農林水産業費、1項農業費、2目農業総務費について、農林産物加工直売所の次期指定管理者に対し、さわらびの湯も運営しているため、2施設の長所を活かし補い合い、利用者サービス向上、交流人口増加、地域活性化につながることを期待していること、
3目農業振興費について、市内の経営耕作面積は約139ヘクタール、うち13ヘクタールが遊休農地、農家数621戸のうち認定農業者は34名、遊休農地活用は大きな課題であり、新規就農者へのマッチング、6次産業化のマッチングツアーやマルシェ開催などの支援を行っていること、ふるさと納税返礼品に登録された商品もあること、
4目鳥獣被害対策費について、サルの囲い罠設置により、群れ自体は縮小しており、被害は減少しているが、引き続き監視が必要なこと、
イノシシやシカの被害は捕獲だけでなく、電気柵の補助金等を活用した防御策の啓発を行っていること、
近隣市では青梅市と狩猟の協力についての協定を結んでおり、日高市と連携した取組はないこと、
アライグマの処理はシルバー人材センターに委託しており、委託回数を減らすことで委託料を減額するもので、捕獲数を減らすものではないこと、
2項林業費、1目林業総務費について、
森林文化都市基金の積立金は1628万7000円を計上、基金条例に基づき森林整備等に充てる予定であること、
森林環境譲与税について、水源地の自治体と都市部の自治体をつなげる取り組みの推進を県に要望していること、
2目林業振興費について、西川材使用住宅等建築補助金の補助メニュー追加は、家具も西川材であることで、店舗を訪れた方々に広く西川材をPRする狙いがあること、新規出店希望者へは産業振興課と連携し、木材加工業とのマッチングも検討していること、
西川材おもちゃ贈呈事業は、新生児400人分、単価7600円を計上、木育の考え方から小さいころから木のおもちゃに触れてもらうこと、保護者への西川材PRも考え、積み木を予定していること、無垢材で角をとるなど事業者と安全性の確保を調整していること、
森林サービス産業補助金を令和6年度予算700万から令和7年度予算500万に減額したのは、特例認定NPO法人埼玉ハンノウ大学への補助が3年目となり、事業内容を精査したためであること、
7款商工費、1項商工費、
1目商工総務費について、ふるさと納税の目標金額は1億5000万円であること、ふるさと納税課と産業振興課が一体となり市内事業者の販路拡大とともに、新たなラインナップを登録したいと考えていること、今年度は1億3000万と見込んでいること
2目商工業振興費について、商店街インキュベーション施設補助金は、まちなかの空きテナントで募集をしていない130軒の所有者にコンタクトを試み、新規出店希望者が一定期間、安価な賃料でお試し出店し、その期間でまちなかの人々との関係性を作ることで、賃貸に難色を示す所有者の不安を解消し、空きテナント活用促進につながると考えたこと、
企業誘致事業について、精明東部地区に指定している用途は工場と物流倉庫だが、物流倉庫の需要が激減し、用途の幅を広げる準備を進めていること、
優先して立地を進める必要があるのは日高市との境に指定している14ヘクタールの土地で、株式会社大平きのこ研究所の向かいの土地は、将来的に指定区域面積を減らすことを視野に入れていること、
新規出店事業補助金と創業支援補助金の要件から市内在住を除き、市外在住でも市内の出店創業であれば補助金活用できるよう考えていること、
3目観光費について、名栗ふるさとまつり協賛会補助金に花火大会開催に要する予算は計上されていないこと、
8款土木費、
1項土木管理費、2目地籍調査費について、地籍調査の予定地区は中山及び原町の一部を含む心のう寺周辺地区であること
4項都市計画費、1目都市計画総務費について、飯能住まい事業は、都市計画法の改正で災害イエローゾーンでの建築が厳格化され、対象となる土地の確保が難しいが地区内には災害イエローゾーン以外の土地もあり、引き続き取り組むこと、都市計画区域外の土地では認定を取得することで手続きが煩雑になり得策でないこと、第二区地区には災害イエローゾーンが多く、精明地区は農業振興地域で農用地区域に指定されており導入のハードルが高いこと、移住定住支援の観点で各種補助金の交付を行っており引き続き政策全般に取り組むこと、
3目街路事業費について、阿須小久保線阿須工区の収用は事業認定申請を行う予定であること、
久下六道線の総事業費は把握後に公表に努めたいこと、整備の必要性は利用者の安全安心と賑わいの復活であり、具体的な指標はないが、飯能まちなか未来ビジョンにより、公民連携で様々な取り組みを推進していくこと、緊急財政対策についての市民の声は、コミュニケーションを図ってきた中では反対意見もなく、境界立会もご協力いただけている状況であり、現状方針で事業を進めていくこと、市としては緊急財政対策の状況を踏まえながら事業を進めること、立体交差の計画は今も残っており、幅員16メートルでの暫定整備の予算となること、幅杭測量は道路の計画線を示す幅杭を現地に設置するもので、地権者ごとの必要な事業面積が明らかとなる為、具体的な用地交渉に向けて進むと考えていること、
4目下水道費について、下水道事業会計繰り出し金の減額は下水道使用料の改定を見越したものではなく、財政当局との調整で市全体の財政状況を踏まえたものであること、
5目公園費について、流れ橋は4月に修繕工事発注し、橋桁2桁を作成して、1日でも早い通行を目指すこと
5項住宅費、1目住宅管理費について、向原団地の跡地利活用方針は未定で、都市計画法上の制約等を整理し民間活力による活用等広く検討していくこと、
等が明らかとなりました。
以上で質疑を終結し、野口委員から「緊急財政対策が必要との方針を掲げながら、本予算案には具体的な財政再建の方向性が示されておらず、例えば政策的経費にあたる久下六道線の拡張工事を、工事全体の予算規模や事業期間も未定なまま、担当課も把握していない状況の中進めるなど、市民目線に立った予算編成とは言えない。緊急財政対策を掲げる以上、公共事業を見直し、財政調整基金の確保と市民生活を守る施策を最優先する予算編成が求められる」という趣旨の反対討論があり、
続いて滝沢委員から「久下六道線整備事業費で、幅杭を打つことは、心に杭を打つことでもあり、あくまで16メートルの整備を進めるためではなく、住民の要求に沿った整備にするべきである。下水道費は、下水道事業会計繰出金が令和6年度予算より1億5千万円の減額、市民生活が厳しい中で下水道料金値上げを計画しながらの減額は認めることができない。」という趣旨の反対討論があり、採決の結果、議案第23号中本委員会付託分は賛成少数により、原案を否決すべきものと決しました。
議案第25号
質疑では、財源確保が難しく、保留地処分金の歳入見込みが厳しい状況から、事業費は減額となっているが、地権者との交渉、生活道路の整備等、事業進捗を図ること、立地適正化計画の策定により補助率のかさ上げ対応が可能となり、重点地区は補助金の内示率も変わってくると考えられ、策定に協力しながら進めていきたいこと等が明らかとなりました。
以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、議案第25号は全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第26号
質疑では、建物移転戸数は5戸を予定していること等が明らかとなりました。
以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、議案第26号は全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第28号
質疑では、元加治駅南口駅前通り線の道路整備は建物移転が完了したのち、早期に着手したいと考えていること、雨水浸透管を整備しており、排水状態を考慮して工事を行っていること等が明らかとなりました。
以上で質疑を終結し、討論はなく、採決の結果、議案第28号は全委員異議なく原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第32号
質疑では、年間総配水量は約0.8%の減を見込んでいること、要因は人口減少、節水機器の普及、物価高騰による節約などの影響と捉えていること、老朽管布設替事業は、川寺地内、芦苅場地内、平松地内を予定していること、赤水対策は稲荷町地内、柳町地内の工事と、長澤地内の更新工事を予定していること、県水の受水量は割合13%で継続していく考えであること等が明らかとなりました。
以上で質疑を終結し、滝沢委員より「年間総配水量も人口も減少する中、県水受水量を減らすべき」という趣旨の反対討論があり、採決の結果、議案第32号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。
議案第33号
質疑では、一般会計繰入金は、下水道使用料の値上げを見込んで計上したものではないこと、下水道事業は厳しい状況にあり、3年ごとに状況を検証し下水道使用料の見直しが必要であると考えていること等が明らかとなりました。
以上で質疑を終結し、滝沢委員より「一般会計繰入金が減額される一方で、下水道使用料の改定により市民の負担は大幅に増える」という趣旨の反対討論があり、採決の結果、議案第33号は賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決しました。